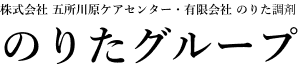言葉の認識👂
人と言葉を交わすとき
認識ズレを起きやすい。
早く・遅く・上手く・よく・ちょっと・
少し、多く、高く、低くなど
普段何気無く、使っている言葉でも
人によって、認識は異なる。
自身の言葉の認識を
相手も同じ認識と
勝手に想像して、誤解してしまう。
後で、
行動を見ると
自身の認識とは
違う行動になってから
気が付いて
再度、認識を合わせようとする。
例として
利用者の気持ちを考えて見守りしましょう
の一文でも
利用者とは、どのような利用者のことか?
気持ちとは、どんな気持ちのことか?
考えてとは、どう考えるのか?
見守りするとは、いつまで見守るのか?
これを言い出したら、きりがないが
たったこの一文でも
これだけの認識ズレを起こす
可能性があり
修正を余儀なくされることになれば
今までの時間が無駄となる。
言葉の認識を合わせるには
それぞれのアウトプットすることが
重要。
それぞれが、話すことにより
認識の齟齬がない状態に近づき、
同じ方向性で動き出せる。
お互いに
言葉の認識を合わせようと
意識するだけで
かなりの行動の違いを
防ぐことになる。
まずは
人の話しに頷くだけでなく、
人から言われるまでなく
自ら言葉を発して、
自身の認識を伝えることで
その言葉の定義が
意味付けられて
お互いに
ストレスなく同じ認識で、行動できる。
言葉の認識を常に合わせましょう。